ヴァン・モリソン
Van Morrison (1945ー)
ヴァン・モリソン? 誰それって? あのねえ、すごい有名なアイルランド生まれのソングライター&シンガーなの。っていうことをこれからアイルランドに行こうとしている友達に言ったら、あんたにとってだけ有名じゃないの、と私のマニアックさを知っているその友人に皮肉られたものだけど、その友人が帰ってきて曰く、「すまん、君が言っていたその音楽家、ダブリンでは 音楽の記念館みたいなところではコーナーがあって超有名だった」って報告されたときはそれは嬉しかった。 つうか、アイルランドではヴァンの記念切手が発売されるたという話。日本の音楽家で切手になるほどの国際的知名度の人っていないよなあ (日本での知名度は低いって? ぐすん、そうなんだよなー)。アイルランドではこんなすごい人がパブとかで普通に歌っていたりするという異常な国らしい。んで、アメリカという国はこの人のアルバムは初登場でチャートの三位にあがったりする異常な国らしい。どっちも危険な国だけど、音楽を愛するということにかけてはレベルが違います。
にしても、ヴァン・モリソンの音楽を聞いたことにない人に紹介するのはすごく難しい。基本的にブルー・アイド・ソウルに分類されて、アイルランド生まれなのでアイリッシュな傾向もあるけど、ちょっと独自の音楽を作り上げている孤高のシンガーです、とか口頭で言おうものなら、かなり入れ込んでいる変な奴に思われる。でも、これが本当なんだよね。日本の音楽ってたいていすごく単純で、ロックならギターとキーボードとドラムズだし、一般的なポップな曲は基本的にどれも同じサウンドの作りをしている。一青窈やたまはほんとに例外ね。んで、ヴァンの下地となっているR&Bを歌う人ってのも極端に少ない。ウルフルズがわずかに本格的なぐらいで、宇多田ヒカルも実は日本のポップスの音調からはみ出ていない。アメリカは黒人音楽だけでも、ジャズにブルース、ゴスペルという異なる音楽的ルーツがあるし、その発展方向もドゥワップにソウルにR&Bと多彩だ。ヴァン・モリソンはアイルランド のベルファスト生まれながらこの黒人音楽への強い傾倒のもとで1964年にゼムというバンドを結成し、その「グロリア」という曲は幾人ものアーティストによって録音された。アルバム二枚を出した後ゼムを抜けてソロになってアメリカに渡り、『アストラル・ウィークス』というロック史に残る名盤を二晩で撮った後、ザ・バンドやドクター・ジョンなどとの交流によってアメリカン・ミュージックをさらに自分のものとしつつ、自分のアイリッシュ性に目覚めたりもしつつ、80年代に入ってからも『Inarticulate Speech of Heart』や『Poetic Champions Compose』など完全に独自のスピリチュアルな境地に至った傑作アルバムを発表しつづけています。評論家の中には彼のアルバムを「全部傑作」と断言する人もいるくらい。実際、どれもほんとにいいアルバムばかりなので信じられない。これだけの質と量でアルバムを発表し続けているシンガーってちょっとほかにいないんじゃないでしょうか。
さて、ヴァンの作品はどれもいいので、どれから聞くのかというのは難しい問題です。私はザ・バンドの『ラスト・ワルツ』での熱唱があまりにもすばらしかったので『アストラル・ウィークス』を買ったらその半年後くらいに一気にはまっていったわけですが……ザ・バンドやボブ・ディランを聞いて育った人以外にこのコースはちょっときついかもしれない。というわけで、ヴァンのポップな名作『ムーンダンス』とアコースィックな傑作『ヴィードン・フリース』、そして『..It's Too Late to Stop Now... 』をお勧めしておきます。『ヴィードン・フリース』にはスタジオ録音でしか味わえない静かなヴァンがいるし、ライヴ版の『..It's Too Late to Stop Now... 』は普通のスタジオテイクよりはるかに素晴らしいライブヴァージョンの熱演が収められており、ベスト盤的な楽しみ方もできます。
アルバム紹介
(あまりにも多いので、簡潔なリストをアマゾンに作りました。その1、その2です。)
全部揃えても六万円ぐらいだと思います。ぜひ大人買いして、毎日癒されてください。
ヴァンのソロデビューアルバム。「Brown Eyed Girl」や「T.B. Sheets」などはや名曲がめじろ押しだが、かなり暗い曲が多い。しかし「Who Drove the Red Sports Car」など『アストラル・ウィークス』に近い曲もある。ジャケットはいかにも安っぽいが、なかなかの傑作。
Astral Weeks(Nov.1968, Warner Bros.)
アストラル・ウィークス彼の原点にして頂点。心の流れそのままのような自在で宙を舞う曲に、ジャズ風のウッド・ベースが利いている。粘り着くような力強い歌声は、トランス状態で歌っているようだ。これがわずか二晩のセッションで録られたことを知ると、一流ミュージシャンたちがヴァンの心に一瞬一瞬反応していく奇跡的な演奏がされていることが判るだろう。 ここで素晴らしいフルートを披露しているジョン・ペイン だけが昔からヴァンとつきあいがあったが、そのほかはヴァンの音楽をぜんぜん知らなかったらしい。全体をリードしているウッド・ベースのリチャード・ディヴィスはエリック・ドルフィーの『アウト・トゥ・ランチ』で演奏していたりもする人。ドラムズのコニー・ケイはMJQのドラマーと、ほんとにジャズの一流の人材を使っている。そういう意味では、一流のロッカーたちをバックに使っているボブ・ディランの『ハイウェイ61レイヴィジテッド』(1967)にちょっと似ている。
でもこの音楽はアコースティック・ロックっぽくもなく、ジャズっぽくはあるけどジャズでもないので、やはり当時のどの音楽にも似ていない。似たようなことをしようとしていたのはジョニ・ミッチェルぐらいかなあとも思う。彼女も独自の音楽を追究しているという点で、まるでヴァンの女性版のような人だとも思うし。
68年にはザ・バンドのファーストアルバムなんかも出ているけれど、完成度という点ではこのアルバムには及ばないと思っている。とゆうか、古今東西でた音楽アルバムのなかでももっとも素晴らしい一枚だと信じて疑わない。楽曲そのものも素晴らしいけど、やはりその演奏が有無をいわせないんよね。
『アストラル・ウィークス』を初めて買ってから毎日聴いていたわけだけど、その何ヶ月か後のある日、このアルバムに莫大な感情が抑圧されつつ込められていることに気がついて、愕然としたことがあった。これほどのロック・アルバムにこれ以降出会えるとは思わない。
とはいえ、まがりなりにもヴァンを聞く人の中にも、これがわかりづらいアルバムだという意見が一番多い。ま、それはそうかもしれないのだけど、そういう意見が多いことからも、やはりこのアルバムは特殊なのだなあと思う今日この頃。
Moondance (1970, Warner Bros.)
ムーンダンスこれを最高傑作にあげる人もいるかもしれない。さまざまなジャンルの要素が混じりあった「ムーンダンス」を初め、バラエティに富んだ音作りになっている。決して古びることのない新鮮な傑作。 「キャラバン」「イントゥ・ザ・ミスティック」などヴァンの定番となる曲の他、「ジーズ・ドリームズ・ユー」とか「エヴリワン」など愛に満ちた曲も美しい。 とゆうか、このアルバムの曲はほんとにどれもすごい傑作です。
どんな好きなアーティストの作品にもたいてい、どうしても好きになれない作品があって、それが私にとってはなぜか一般に評価の高いアルバムだったりして、『サージェントペパーズ』や『ハーヴェスト』だったりするのよね。んで、ヴァンだとこの作品あたりあんまり好きになれなくってもよさげなんだけど、そうじゃないんだよね。これはビートルズの『ラバーソウル』みたいなアルバムで、ぜんぜん浅くない。
この時期のヴァンについて、一般への妥協だとか、自分の内面的な音楽から少し離れて作られたアルバムだとゆう見方があるが、ぜんぜんそんな感じはしない。ただすでにある音楽を使って作ったアルバムってすぐに分かるんだよね。ヴァンのはどれも完全に自分のものにして、それを愛しきって素材にして音を作っている感じがする。それに、この時期はアメリカン・ミュージックを彼なりに掘り下げていく時期にあたっており、彼の音楽人生の中でも重要な時期であるには違いないんだよね。ここで開拓して音楽的に豊かになったからこそ、あとで自分の音楽が作れるようになったんだと思います。Rocks His Gypsy Soul: Van Morrison Gets His Chance to Wail, Vol. 3
ブートレックで手に入る音源で、1970年4月26日にフィルモア・ウェストで行われたライブの記録。この時代のライブのマテリアルとしては唯一のもので、音質もよいので公式なリリースがあってもよいのだが……。ゼム時代の曲はなく、この時点でソロで出している三枚のアルバムの中から代表曲を演奏している。CDにはボーナストラックも収録されている。
His Band and The Street Choir (Oct.1970, Warner Bros.)
ウッドストックで暮ら していた時期の作品で、ザ・バンドの連中とのつきあいから生み出された作品らしい。確かに、アメリカン・ミュージックへの愛情表現になっている。「ドミノ」など、 ホーンセクションなどを使ったR&Bの曲が多く、神秘的な感じはしないし、前の二作ほど革新的でもないが、安心できる暖かさに溢れている。いつでも迎えてくれる家族というか、そんなフレンドリーな感じ。これはヴァンがアイルランド出身だから出せる雰囲気なのかしらん。
明るいナンバーが多いんだけど、後半の展開はぐっとくる。鉄琴が印象的なGypsy Queenなんかもすごい好きだし、スローなバラードのIf I ever needed someoneも味わい深い。こういういろんな曲調が入っているからいいんだよなあ。後者の曲は宗教的な歌で、のちのモリソンを予感させるとかなんとか言っておこうかな。そして最後のStreet Choirは切々とした名曲。ウッドストックのミュージシャンを使った最後の作品なのかな。
Tupelo Honey (1971, Warner Bros.)
『テュペロ・ハニー』幸せ溢れるアルバムで心地よい。サン・フランシスコで録音されたので、ミュージシャンも東海岸の人を使っている。ヴァンの最も幸福な時期に録音されたであろう、ラブソングが多いこのアルバムをことのほか愛するファンも多いはず。「ワイルドナイト」「アイウォワナルーユー」「ムーンシャインウィスキー」とか ついつい一緒に歌いたくなる曲が多くて困ります。「You're My Woman」と「テュペロ・ハニー」はヴァンのラブソングの中でも最も素晴らしいでしょう。ヴァンの初期の作品のなかでもとりわけ気楽に聞くことのできる明るいアルバムです。ジャケットも美しい。
Saint Dominic's Preview (1972, Warner Bros.)
『セント・ドミニクの予言』ストリングスを導入したこのアルバムは、全三作に比べると、かなり自由な曲作りがされているように思える 。「ジャッキー・ウィルソン・セッド」のようなR&Bだけじゃなく、タイトル曲みたくゴスペルっぽい曲もある。
このアルバムでヴァンはそれまでにポップ路線から抜け出し、独自の「カレドニアン・ソウル」と名付けたジャズ、R&B、ソウル、ゴスペルなんかをごちゃまぜにして昇華したサウンドを作り出そうとしている。んで、その方向は『アストラル・ウィークス』で見せた精神的な方向へとも向かうのでした。「リスン・トゥー・ザ・ライオン」とタイトル曲をまあ聴いてみてよ。とても内向的でありながら同時にこのヴォーカルの力強さ。たいてい、こういう精神的な方へ行くとつぶやくよーな歌声になるものなんだけどね。レナード・コーエンしかり、同じくソウルなマーヴィン・ゲイもそうだし。このへんがヴァンの真に独自なところだと思います。やっぱりロックしてるんだよね。最後の「オールモスト・インディペンデスンデイ」は神秘的な雰囲気の曲で、パフォーマンスも非常に素晴らしい。これを聴いているとほんとにヴァンの魂に触れているような気がするから不思議。というわけで、ヴァンを語る上ではやっぱり欠かすことのできないアルバム。でも真ん中の二曲は、『魂の道のり 』でのライブパフォーマンスも素晴らしいんだけどね。
ところで、オープニングタイトルの「Jackie Wilsson Said」なんだけど、ジャッキー・ウィルソンはエルヴィス・プレスリーやマイケル・ジャクソンが手本にしたというソウルの大御所。もちろんモリソンも影響受けてるはずだけど、なぜここで登場するのかは謎です。
Hard Nose The Highway (1973, Warner Bros.)
『苦闘のハイウェイ』『アストラル・ウィークス』と『ヴィードン・フリース』という二枚のアコースティックな超傑作にはさまれた『ムーンダンス』からこの『苦闘のハイウェイ』 までの五枚のアルバムは、ヴァン・モリソンの第一期の創造的なピークに作られたアルバム群だと言える。この数年間のアメリカ生活の間にヴァンはウッドストックやサンフランシスコにおいて様々なアメリカ音楽とのつきあいを深めてより自分のものにしつつ、それに彼のアイリッシュかつ独自な味付けをほどこしていった。この間の五枚のアルバムは音楽的にもとても多彩で、どれも傑作なのにはほんとに驚かされる。このアルバムではさらに、彼が作ったカレドニアン・ソウル・オーケストラがすべての曲でバックにつき、彼の目指したサウンドが完成しつつあることが伺える。
このアルバムは前の四作に比べると楽曲にあまりまとまりがないせいで、少し評価を下げられている。しかし、歌唱隊を全面にとりいれた冒頭の「サン・アンセルモの雪」のすばらしさは今までのアルバムには見られないものだ。コーラスだけでなく、ウッドベースもまた素晴らしい。二曲目の「ウォーム・ラブ」は彼の代表曲の一つで、フルートが独特な雰囲気を加えている。四曲目の「ワイルド・チルドレン」はハリウッドを歌った曲(どうしてこの時期はマーロン・ブラントのことを歌っている人が多いんだろうか……)。五曲目の「グレートデセプション」は彼らしい、世間の欺瞞に嫌けがさしていることを歌った曲。六曲目の「ビーイン・グリーン」はシナトラの歌をジャズ風味で歌っている。表題曲も含めてメッセージ性のある曲が多く、どこか憂愁を帯びたナンバ ーが多いのもこのアルバムを印象深いものにしている。とくに最後の二曲はヴァンマジックが炸裂した曲で、「オータム・ソング」は同じフレーズが繰り返される長い魔術的なナンバーで、「Purple Heather」はアイリッシュ・トラディションをヴァンが編曲したもの。
カレドニアン・ソウル・オーケストラはホーン・セクションとストリング・セクションに加えてジョン・プラタニアなどの少数のリズム・セクションがバックを支えるという編成。といってもつねに全員が演奏しているわけではなく、要所要所に音を使っている。このサウンドの作り方には洗練されたウェストコーストミュージックの香りがある。ヴァンはカレドニアン・ソウル・オーケストラで71年にツアーをしているが、このアルバムではそのツアーの音をスタジオアルバム作りに注入している。ノリはライブなので、できるだけ大きな音で聞くとより楽しめるようになっている。とくに、「Purple Heather」を大音量で聞いているとヴァンの「ダダダダダダ……」といううなり声のような歌声に涙してしまうから不思議だ。
カレドニアン・ソウル・オーケストラをフルフューチャーしたこのサウンドの方向性としては、このアルバムは必ずしも決定的な傑作とは言えないかもしれない。これはヴァンは数年間追求してきたものだけに、この方面の決定的なスタジオアルバム作品がないのは残念だが、そこは次の傑作ライブアルバムが化わりをつとめている。
さて、これもデジタルリマスターされたCDが出ているんだけど、もうほんとに音がクリアになっていて感激ものです。ギターのタッチなんか鮮明に聞き取れる。最近は日本版出てないのね……私は持ってるけど(ボソ)。
...It's Too Late to Stop Now... (1974, Warner Bros.)
『魂の道のり』カレドニアン・ソウル・オーケストラと共に行われたライブ盤。スタジオ録音よりはるかにテンションの高い歌いっぷりが最高。 ロックのライブアルバムの中でも間違いなく最高のものの一つだろう。トータス松本も歌うBRING IT ON HOME TO MEとかブルースの名曲などもとりあげているが、それもその曲のベストレコードと言える出来映えになっている。あらゆるブルース/ソウルシンガーにとって到達しえぬレベルではないでしょうか……恐ろしい。
Veedon Fleece (1974, Warner Bros.)
『ヴィードン・フリース』ヴァンの自己回帰的作品で、ターニングポイントとなった。『アストラル・ウィークス』と双璧をなす傑作。ヴァンがアイルランドに帰郷した時、自身のアイデンティティに目ざめて作られた。リコーダーの響きがアイリッシュっぽい。テンポはゆるめ 。このアルバムに巡りあうことができた幸運に感謝するしかないような、そんな比類なく神秘的かつ感動的な作品です。 愛する妻との離婚をへて作られた音楽だけど、『アストラル・ウィークス』のような痛みは音楽にはなく、むしろ深い精神性からくる繊細な安らぎのようなものを感じさせます。
ジャジーなウッドベースとピアノが印象的なオープニング・タイトルのFair Playには今までの作品のようなホーンは聞かれず、ヴァンもスローに歌い上げるような歌いっぷり。これがほんとによい。このしょっぱなを聞くだけで、ヴァンがここですでに独自の世界を創りあげていることが分かるはずだ。同じテイストの「Linden Arden Stole the Highlights」ではストリングスが入り、世界が広がる。これはアイルランドからアメリカに渡ったならずものの話で、これがメドレーのように「Who Was That Masked Man」につながり、「銃だけを信頼して生きるなんて寂しくないかい」と歌われる。ここでのファルセットボイスはニール・ヤングを少し思わせる。「Streets of Arklow」ではフルートが導入されて、美しいアイルランドが情感豊かに歌われる。ストリングスの展開がほんとに心地よい。「You Don't Pull No Punches, But You Don't Push the River」はウィリアム・ブレイクと聖人たちが慈悲の女神のところに行って「ヴィードン・フリース」を探し求める……という不思議なリフが繰り返される催眠術的な曲。後半の一曲目は、はじめてドラム ズやエレキギターが入るカントリー・ロック風の「Bulbs」。この曲の最後では「すべてはショウビズさ」という言葉が吐かれてびっくりする。最後の鼻歌がすごい「Cul de Sac」、穏やかな「Comfort You」、そしてギター一本で歌う「Come Here My Love」と続き、最後の「Country Fair」まで聞くと、なんだかひどく内省的な叙情詩を読み終えたような気になる。
A Period of Transition (1977, Warner Bros.)
『安息への旅』アメリカでの活動の第二期のはじまりに作ったアルバム。ドクター・ジョンとの共同プロデュースで彼はピアノも弾いている。R&Bを全面に押し出した作品で分かりやすく聞きやすいのだが、ヴァンの作品の中では凡作とされている。確かに初めて聞いたときはそういう印象を受けた。ヴァンの声は前作のような魂に触れてくるような神秘的な雰囲気がないし、バックの演奏も平板でカレドニア・ソウル・オーケストラのような多彩さがない。でもそのぶん、普通にノレる音楽になっていて、聞いているとだんだんけっこう気に入ってきたから不思議だ。
ヴァンの作品のなかで凡作とは言っても、普段のヴァンのアルバムが持っているような高度な精神性を感じさせないという意味が強くて、普通のR&Bとして聞けばけっこう聞けるのだ。とくに「ジョイヤス・サウンド」は完全に成功しているし、「ヘヴィ・コネクション」なんかも名曲だ。というわけで、ヴァンのコアなファンにとってはもっていてもいい作品なのです。
Wavelength (January 1, 1978, Warner Bros.)
ウェイブレングス
The Band, Last Walts, April 1, 1978
ラスト・ワルツヴァンとザ・バンドとのつきあいは長くて、71年には彼らのアルバムにリチャード・エマニュエルとの共作「4%パントマイム」を提供したりしている。そのヴァンがザ・バンドの歴史的解散コンサートに出演したときの音源がこれ。
私とヴァンとの出会いはこれの映画版で、とにかく熱唱して全身を使って歌うヴァンの姿は無茶苦茶強烈で、なんなんだこいつは〜と思った記憶がある。しかしほんとにここでのヴァンは一世一代の熱唱だと思う。ヴァンは「アイルランドの子守唄」と「キャラバン」のテイクが入っている。「アイルランドの子守唄」は他で歌っているのを知らないので、とても貴重だ。1979 Live at the Roxy
Into The Music (1979, Mercury)
『イントゥ・ザ・ミュージック』ヴァンのベストアルバムの一つ。これ以降のヴァンの作品はかなり聞き込まないとよさが分かりにくい。
実はヴァンが創造的なピークにあったときに発表された異色作。
彼の故郷アイルランドのことを多く歌った、フォークとブルースを下敷きにしたアルバム。シンセイサイザー(Mark Isham)がフューチャーされている。ホーンセクションはバックサウンドとして使われているが、何度も繰り返し聞かないとそのパターンには気づかないだろう。女性ゴスペル・トリオのバックヴォーカルも全曲にフューチャーされているが、ヴァンの歌声は彼女らによりそうように穏やかなものだ。全体として興奮にかけていると思えるかもしれないが、このアプローチはとても効果をあげている。
パイプ(Sean Fulsom)が冒頭の二曲に使われていて、ケルトな雰囲気を醸し出している。『Irish Heartbeat 』においてセルフカヴァーされる「Celtic Ray」はアイルランドからの呼びかけの曲で「I've been away too long」と歌われる。「Northern Muse (Solid Ground)」も故郷を題材にした曲。「Dweller on the Threshold」は<永遠の平和を待ち望むために待つ>という意味の曲。これはAlice Baileyの『Glamour: A World Problem』というグノーシス主義の本が下敷きになっているそうで、「Aryan Mist」もそう。これらの曲はヒュー・マーフィとの共作になっている。Chris Michieのギターと「裁きの日」のトランペットはまるで天国の勝利のように響いている。
「Beautiful Vision」は神秘的な雰囲気のナンバーだが、「Cleaning Windows」は即興的な暖かい曲で、Mark Knopflerが率いるリズム隊は軽快で、ホーンが吹くのは伝統的なsoul/R&B。このユーモラスな曲はJimmie Rodgersなどを聞きながら窓ふきの仕事をしていた時代のことを思い出している。ラストの「Scandinavia」はなんとインストゥメンタルで、ピアノをヴァンが弾いている。
Inarticulate Speech of the Heart, 1983
『時の流れに』ヴァンがスピリチュアルな高みに達した作品。この後、引退宣言なども飛び出した。
Live at the Grand Opera House - Belfast(1985,
A Sense of Wonder(1985)
『センス・オブ・ワンダー』
No Guru, No Method, No Teacher(1986, )
Poetic Champions Compose (1987, )
Irish Heartbeat (1988, Mercury) with The Chieftains
Avalon Sunset (1989, Polydor)
Hymns to The Silence (1991, Polydor)
ジョン・リー・フッカーと競演しつつ作ったブルース・アルバム。ブルース色の強いアルバムでなんだけど、女性コーラスがちょっとひどい。肝心のジョン・リー・フッカーの声も完全に衰えていて、一緒に「グロリア」を歌っているけどフッカーは邪魔しかしていない。うーん……これはちょっと。自分の音楽にうるさいヴァン・モリソンがこんなテイクを入れるなんて、ちょっと信じられません。「グロリア」は聞くに堪えないので、曲リストからはずして聞いています。ほかのカバーの曲はいいけど、オリジナルの曲はあんまりよくないです。
1995 Days Like This
1996 How Long Has This Been Going On
ヴァンがジャズをやったアルバム。ムーンダンスなんかもジャズ風にやっている。1996 Tell Me Something: The Songs of Mose Allison
1997 The Healing Game
ヒーリング・ゲーム久しぶりのオリジナル曲でのスタジオアルバム。オープニングタイトルなど確かにいい曲もあるけど、そんなに魂に響くようなアルバムではないんだよなあ。バックの演奏も平凡で、バックコーラスのブライアン・ケネディも声を出しているだけという感じ。四曲目の 、バグパイプを使った「Waiting Game」なんかは好きなんですけど……。いつも同じことやってるだけ、という皮肉な評もちらほら。うーん……
1999 Back on Top
2000 The Skiffle Sessions: Live in Belfast 1998
2000 You Win Again
Down the Road(2002, Universal)
What's Wrong With This Picture(2003, Blue Note)
リンク集
公式HP あるんだな、これが。新譜のさわりとか聞けるので、感じをつかみたい方はこちらへ。
AVALON SUNSET 日本唯一のファンサイト。アルバム情報など。
THE VAN MORRISON WEBSITE すんごい辛口のアルバム評、歌詞、用語集など。
Wavelength ヴァンファンのためのヴァンファンによるMLサイト。入るといいことあるかも。
Into The Music 最も充実したヴァンサイト。コンサート情報も詳しいです。
![]()
 1967
Blown' Your Mind!
1967
Blown' Your Mind!
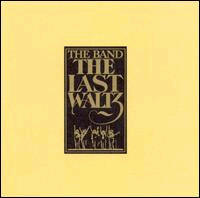

 Beautiful Vision,
1982
Beautiful Vision,
1982
 Too Long in Exile(1993)
Too Long in Exile(1993)